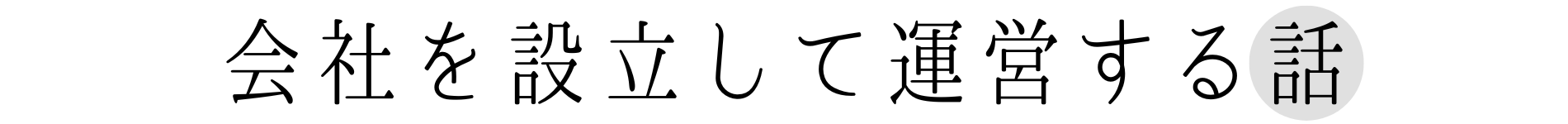step4. 社会保険等の届け出|雇用後に必要な社会保険・労働保険の届け出と書類管理
かなえ:「今回は、人を雇ったあとの役所への届け出のお話ですね。
会社設立後の届出のときのような書類の山をつい想像してしまってびくびくしてます。」
いち:「はい、行政機関にどんな届出をしなければならないかと共に、会社で管理が義務付けられている書類の説明もしたいと思います。
決まっていることをこなせばいいだけですからそんなに心配しなくても大丈夫ですよ!
ただし、正しく届け出をしないと、罰則があったり、従業員の保障が受けられなくなったりすることがありますのできちんと行いましょう。」
雇用後すぐに必要な届け出一覧
いち:「まずは、従業員を雇用した後に必ず届け出をしなければいけない書類です。」
従業員雇用後に会社が必ず行う公的手続き一覧
| 名称 | 期限 | 届け出先 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した日から10日以内 | ハローワーク (公共職業安定所) | 新たに労働者を雇用した際に提出する雇用保険加入手続き |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 資格取得日(その人が社会保険に加入すべき義務が発生した日)から5日以内 | 日本年金機構 | 健康保険と厚生年金保険の被保険者手続き(条件を満たす労働者) |
| 労働保険概算保険料申告書 | 新規事業開始から概ね50日以内 | 労働基準監督署 またはハローワーク | 労災保険・雇用保険の保険料見込み額の申告(新規事業など) |
| 労働保険年度更新申告書 | 毎年6月1日〜7月10日 | ハローワーク・労働基準監督署 | 前年実績に基づく労働保険料の申告・納付(毎年必要) |
| 就業規則の作成・届出 (常時10人以上の事業所) | 労働基準監督署 | 従業員10人以上の事業所は就業規則を作成し届出 |
会社が保管しなければならない労務関連書類とは?
いち:「次に、雇用後に会社内で管理する法的な義務がある書類を挙げます。」
| 書類名 | 法的根拠 | 保存期間 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 労働者名簿 | 労働基準法第107条 | 退職後3年間 | 従業員の基本情報・履歴・雇入日などを記録 |
| 賃金台帳 | 労働基準法第108条 | 3年間 | 賃金・手当・控除額などを記録 |
| 出勤簿・タイムカード | 労働基準法第109条 | 3年間 | 労働時間の実績を記録する帳簿 |
| 労働条件通知書 | 労働基準法第15条 | 明記なし(3年程度が目安) | 労働条件の明示書類 ※本人に交付義務あり |
| 就業規則 | 労働基準法第89条 | 常時備え付け | 常時10人以上の事業場に作成・届出義務あり |
| 36協定書 | 労働基準法第36条 | 有効期間後3年間 | 時間外労働の合意書。労基署に届出・保管が必要 |
| 健康診断結果 | 労働安全衛生法 | 5年間 | 定期健康診断などの記録(産業医の意見書含む)※一年に一度の健康診断は会社の義務 |
| 労災保険関連書類 | 労災保険法 | 3~5年間 | 労災発生時の報告書や請求書など |
| 年次有給休暇管理簿 | 労基法施行規則 | 3年間 | 有給休暇の取得日数・残数などの記録 |
任意の届出|トラブル防止に役立つ実務上のおすすめ
いち:「さらに、法的義務はなく作成は任意ですが、実務上重要な書類を整理しておきましょう。
トラブルを避けるためにも作成を推奨します。」
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 雇用契約書 | 労働者と会社双方が署名する契約書。トラブル防止のため作成推奨 ※はじめての雇用編3参照 |
| 誓約書 | 守秘義務・競業避止義務など、法令順守を誓約する書面 ※はじめての雇用編3参照 |
| 身元保証書 | 従業員による損害に備えて連帯保証人を付ける書面(上限額の記載が必要) ※はじめての雇用編3参照 |
| 社会保険関係届出の控え | 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入届などの控えを保管 |
| 雇用保険被保険者台帳 | ハローワーク提出後の被保険者記録の写し |
まとめ|雇用をするまでの手続きはこれで完了
かなえ:「ふう…、やっぱり種類の山になるんですね…」
いち:「確かに種類は多いですけど、提出先ごとに整理しておけばそれほど難しい内容ではありませんので頑張ってくださいね!」
かなえ:「たしかに書類の意味と目的を知っておくと、混乱がなくやるべきことがはっきりします。
なによりも一覧表になっていると助かりますね、チェックリストとしても使えますし。」
いち:「それはとても良い方法ですね、ぜひそのように使ってください。
次回の、step5. 退職時の手続きで雇用編は最後になります。
社員が退職したときに慌てないためにも、あらかじめ覚えておきましょう!」