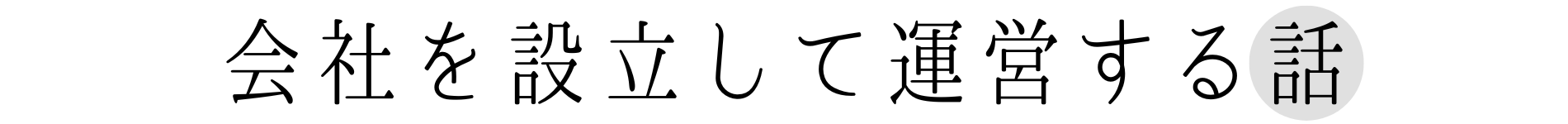step6. 社員の退職時に必要な手続きと会社の対応
いち:「雇用編の最後に、従業員の退職時に必要な手続きについて説明します。
まずは、“従業員に退職の意思を伝えられてから”の一連の流れを整理しておきましょう。」
従業員に退職の意思を伝えられてから退職までの一連の流れ
step.1 社員から退職の申し出があったときの対応を確認する
step.2 退職までに、従業員が行うべき手続きと、返却物の確認
step.3 社員の退職後、会社が行うべきこと
step.4 退職日に会社から社員に各種書類を渡す
step.5 退職後、会社が行政機関へ届け出
step.1 社員から退職の申し出があったときの対応
かなえ:「一緒に頑張ってきた社員に退職をしたいといわれたら動揺してしまいそうです。
まずは、考え直してもらう様に説得をしたらいいんでしょうか?」
いち:「そうですね。それも大切ですが、あらかじめ対応を整理して用意しておきましょう。
以下のような手順を用意しておいたらいかがでしょうか。」
◆社員から退職の申し出があったときの対応◆
1 意思の明確化。退職の意思が曖昧な表現、例えば辞めようか悩んでいる等である場合は、合意ができるようなら引き留めも。
2 退職理由の中にパワハラ・セクハラ・労働条件違反が含まれている場合は、内部調査・記録保存など適切な対応をとる。
※放置をすると労基署への申告や訴訟に発展するケースあり
3 自社の就業規則・雇用契約書に定められた退職の手続き・予告期間を確認。
4 本人の退職希望日と会社の就業規則・業務の都合をすり合わせ、最終出勤日を調整。
5 残っている年次有給休暇の消化希望を確認。
※労基法第39条により、原則としてこれを拒むことは不可です
step.2 退職までに、従業員が行うべき手続きと、返却物の確認
いち:「退職の意思を確認して合意をしたら、そのあと従業員がやるべき手続きや提出物をきちんと伝えておきましょう。
こちらがスムーズに進まないと、会社側の次の手続きに移れないこともありますから、状況によっては軽く催促することも必要になってきます。」
| やること | 備考 |
|---|---|
| 退職届の提出 | 口頭ではなく書面で提出が基本 自社のテンプレートを作っていてもよい |
| 引き継ぎ業務の実施 | 業務マニュアルの作成など |
| 貸与物の返却 | PC・制服・社員証など |
| 離職票の受け取り希望の確認 | 失業手当受給に必要 |
| 健康保険証の返却 | 本人・扶養者分も含め返却 |
step.3 社員の退職後、会社が行うべきこと
いち:「では次に、従業員が退職するときに会社側がやらなければならない手続きについて説明しますね。」
| やること | 概要 |
|---|---|
| 退職届の受理と保管 | 社内文書として保存 ※労基法改正に基づき2024年4月施行で保管期間が5年に延長(中小企業は当面3年) |
| 退職日までの給与計算 | 未払い賃金、有給休暇の清算 |
| 退職金の支払い処理・税務処理 | 退職金制度がある場合のみ 支給があれば、退職所得控除、給与とは別の分離課税の処理が必要 |
| 健康保険証の回収 | 扶養家族分も忘れずに! 退職日に健康保険証を回収し、退職日の翌日から5日以内に資格喪失届を年金事務所に提出します ※健康保険の任意継続は可能 |
| 貸与物の確認 | 業務で作成した資料等を含み返却漏れ・破損の確認 |
| 各種書類の交付 | 退職証明書、源泉徴収票、離職票など |
step.4 退職日に会社から社員に各種書類を渡す
いち:「従業員の退職に伴い、会社から(または行政機関経由で)従業員に渡す各種書類を整理しておきます。」
| 書類名 | 会社の義務か任意か | 従業員の提出先 | 内容・目的・備考 |
|---|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 義務(所得税法第226条) ※退職後1ヶ月以内の交付義務 | 転職先、税務署、確定申告 | ・退職年の給与、控除額を記載 ※年末調整未実施の場合は確定申告で使用 |
| 離職票(Ⅰ・Ⅱ) | 従業員が希望する場合義務 ※会社は基礎資料としてハローワークに「離職証明書」を提出 | ハローワーク | ・失業給付の手続きに必要 ※ハローワーク発行後、従業員に渡る |
| 退職証明書 | 従業員が請求した場合義務(労働基準法第22条) | 転職先、各種手続き | ・在職期間、業務内容、賃金など ※請求があれば遅滞なく交付 |
| 健康保険資格喪失証明書 (または資格取得・喪失確認通知書) | 任意(必要に応じて) | 市区町村、転職先 | ・国保切替、転職先の社会保険加入で必要 ・会社が発行することが多い実務書類 |
| 雇用保険被保険者番号が分かるもの (雇用保険被保険者証の写し等) | 任意(実務上は提供することが多い) | ハローワーク、転職先 | ・失業給付や再就職手続きに必要 ・現在はオンラインで照会される場合もある |
| 最終賃金明細 | 任意(実務上は交付が望ましい) | 本人保管 | ・給与・残業代・未払い分・退職金等の内訳 ・金銭トラブル防止に重要 |
いち:「参考までに、以前は必要だった書類には以下があります。
2022年以降、年金手帳廃止によって会社の義務がなくなったものです。」
| 書類名 | 会社の義務か任意か | 社員の提出先 | 内容・目的・備考 |
|---|---|---|---|
| 基礎年金番号通知書またはマイナンバー | 本人保管(会社が交付する義務なし) | 日本年金機構等 | 基礎年金番号はマイナンバー等で確認される |
いち:「一般的な退職証明書は以下のように作成します。」
退職証明書の作成例
退職証明書
氏名:〇〇〇〇
生年月日:○/○/○
在職期間:○/○/○ ~ ○/○/○
職種(業務の種類):○○職
役職(地位):〇〇〇〇
最終賃金:月額 ○○円
退職日:○/○/○
退職理由:〇〇〇〇
上記のとおり、退職に関する証明をいたします。
○○年○月○日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇
住所:〇〇〇〇
電話番号:〇〇〇〇
いち:「“従業員が希望した場合”とある失業保険関係の書類は、従業員の意思確認をせずに会社から渡すケースもあります。」
step.5 退職後、会社が行政機関へ届け出
いち:「従業員の退職後には行政機関への届け出が必要になります。
期限があるので、速やかに行いましょう!」
| 書類名 | 提出先 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険 被保険者資格喪失届 | ハローワーク ※電子申請対応あり | 退職日の翌日から10日以内 | 退職に伴い雇用保険資格を喪失したことを届け出る ※失業給付の前提となる手続き |
| 離職証明書 | ハローワーク | 希望があれば作成・交付 | 離職理由、賃金情報などを記載 これを元にハローワークが離職票(Ⅰ・Ⅱ)を作成 ※離職票は会社が従業員に直接渡すのではなく、ハローワークが郵送または交付 |
| 健康保険・厚生年金保険 資格喪失届 | 年金事務所・ 健康保険組合 | 退職日の翌日から5日以内 | ・社会保険の資格喪失の手続き ・資格喪失日(退職日翌日)を届け出る ※年金事務所へ健康保険証を返却する |
はじめての雇用編まとめ|雇用を学んでわかった“人を雇う”ことの責任と覚悟
いち:「これで雇用についてのお話は一通り終わますが、かなえさんが最初に“雇うかどうか迷っている”と言っていた気持ちに、何か変化はありましたか?」
かなえ:「はい、最初は仕事が増えたら人を雇えばいいかな、くらいに思っていたんです。
でも実際は…会社としての責任も従業員の人生に関わる責任も想像以上に大きいんだって分かりました。」
いち:「そうなんですよ。雇用って、単に人手を増やすというだけの話ではなくて、その人の生活やキャリアにまで関わる重大な決断です。
会社にとっても、将来の方向性を左右するターニングポイントになりますし、軽くは扱えません。
でも、その分大きな成長のチャンスにもなるんです。」
かなえ:「給与や社会保険もそうですけど、育成や評価制度まで考えなきゃいけないなんて、本当に会社をつくる以上の覚悟が必要なんだなって感じました。」
いち:「おっしゃるとおりです。ただ、適切な給与、育成の仕組み、公正な評価制度、こうしたものを整えることは、決して従業員だけのためではありません。
中長期的には会社自身の成長や利益に直結します。
だからこそ、経営者としてしっかり向き合う価値があるんですよね。」
かなえ:「はい、雇用って、従業員だけじゃなくて自分自身の学びと成長にもつながるんですね。
なんだか気が引き締まりました!前向きに雇用を考えてみたいと思います!」
いち:「責任の重さを理解したうえで前向きに取り組める経営者は、きっと良い会社をつくっていけると思います。
かなえさんの会社の未来を、これからも応援していますよ!」
はじめての雇用編終わり。
はじめての雇用編番外編はこちら