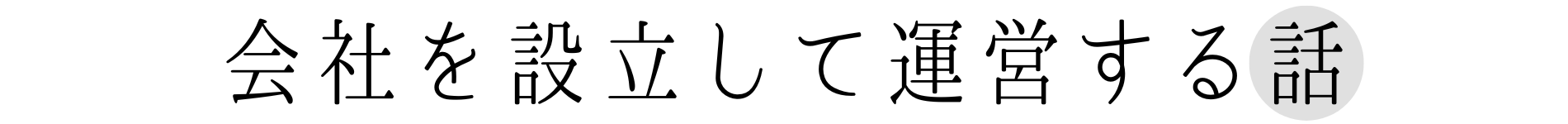登場人物紹介
いち
行政書士事務所所長の行政書士
かなえ
起業の夢を無事かなえたWEBデザイン会社経営の女性 ー会社設立編はこちら-
ジョブ型とメンバーシップ型とは
かなえ:「いちさん、最近SNSでアメリカみたいに解雇しやすくすべきっていう意見をよく見ませんか?でもそれって現実的な話なんでしょうか?」
いち:「では今回は、雇用について少し掘り下げて考えてみましょうか。
そもそもスペシャリストが求められるアメリカと、会社から総合的な能力が求められる日本では働き方自体に根本的な違いがあります。
主にアメリカで採用されている、いわゆるジョブ型雇用(アングロサクソン型)は日本に合わないという見かたもありますね。」
かなえ:「ジョブ型ですか、何となく聞いたことがあります。」
いち:「職務(ジョブ)に人を当てはめ、評価や報酬も成果で決まる雇用スタイルです。
転職しても同じような仕事ができるので会社が違っても成果が出しやすいという特徴があります。
たとえば、ITエンジニアやマーケティング職、営業職などがいい例ですね。
つまり、目に見える成果が出せる方は転職がしやすいわけです。
一方、日本のメンバーシップ型は、終身雇用やゼネラリスト(総合力)重視の考えが根強いですし、再雇用のされやすさもアメリカほどではありません。」
かなえ:「成果で評価するのは合理的にも思えますけど、誰でもそう簡単に転職できるわけじゃないですもんね。」
いち:「そうなんです。結果的には、失業者が増えて社会保障費を圧迫する可能性が高いですし、経済格差が広がるリスクがあります。
様々な意見があると思いますが、アメリカなどがいい例ですよね。
だから簡単に導入すべきではないという意見も多いんですよ。
では、ここで、欧米のジョブ型と日本のメンバーシップ型の違いを整理してみましょうか。」
ジョブ型とメンバーシップ型、比較一覧表
| 比較項目 | ジョブ型雇用 (欧米型) | メンバーシップ型雇用 (日本型) |
|---|---|---|
| 採用基準 | 職務内容に即したスキル・実績を重視 | ポテンシャル(将来性)や人柄を重視 |
| 配属・異動 | 職務が明確に定義され固定 | 職種や部署の異動が前提 |
| 評価・報酬 | 成果主義 職務ごとに報酬が設定される | 年功序列が根強く、総合的に評価 |
| 昇進・昇格 | 成果・専門性に応じて昇進 | 勤続年数や社内評価が重視される |
| 雇用の安定性 | 成果が出ないと雇用終了の可能性あり | 終身雇用が前提 雇用が安定している |
| 育成方針 | 即戦力前提 自己研鑽が中心 | 企業内教育(OJT)を重視 |
かなえ:「こんなに違うんですね…!」
いち:「2025年現在、ジョブ型雇用への移行を進めている日立、資生堂などの大手企業の増加、という現実はあるんですが、一般に浸透するかどうかは意見が分かれるところでしょうね。」
かなえ:「でも経営者の視点でみると、会社に合わない人を解雇して会社に合う人を再雇用する、というのを魅力的にも感じるのは分かるような気がします。」
いち:「そうですね、なのでSNSでは経営者のこの手の意見が出てくるのだと思います。
あまり深く考えずにこの考えに迎合する人がいるのだろう、というのも想像に難くないです。
でもそれは、先に述べたように経済格差の大きな要因にもなるでしょうし、その結果、巡って経営に影響を与えることにもなりかねないので、慎重に議論を進めていくべきなのでしょうね。」
賃金が上がらないのは解雇ができないから?
かなえ:「解雇ができないことが日本では長らく賃金が上がっていない理由だと言われていることについてはどう考えますか?」
いち:「確かに、解雇がしづらいから賃金が上がらないという面もあるかもしれませんが、それが賃金停滞のすべての原因とは言えないと思います。
理由の一つとして、日本は長年デフレが続き経済全体の成長が鈍化していたため、企業側も大きな賃上げの判断がしづらい環境だった、という背景があります。」
企業の内部留保ってなに?
かなえ:「なるほど、企業にお金がないから賃金を上げることができないということですね。
でも以前ニュースで、企業の内部留保が過去最高になったというのをみたことがあります。
それらを社員に還元するという話にはならないのでしょうか?」
いち:「財務省の法人企業統計で、2023年度には企業の内部留保が600兆円(利益剰余金ベース)を超えたとの発表がありましたね。※2024年9月3日時事通信社
内部留保が積み上がり、それが社員の給与に反映されていないのは一部企業では事実なのでしょうが、多くの企業にとっての内部留保の増加は、決して“現金が会社に増え続けている”という意味ではないんです。」
かなえ:「内部留保が増えるということは、企業の利益の過剰分を社員に還元せず貯めておく、ということかと思っていました。」
いち:「確かにそういう企業もあると思います。
しかし、内部留保は、設備投資や借金返済に使われていることも多くて、すぐに賃金へ回せるとは限らないのが実情です。
特に中小企業は経営の不安定さに備えてある程度の蓄えを必要としています。
内部留保の内容は企業によって違い、一律には判断できないものなんですよ。
つまり、内部留保の増加は多くの企業の体力の無さの反映でもあるわけなんです。
参考までに、一般的に内部留保の内訳は以下のようになるケースが多いです。」
内部留保の内訳一覧表
| 内部留保の主な内訳 | 内容 | すぐ使える? |
|---|---|---|
| 現預金 | 手元にある現金や銀行預金 | ◯(すぐ使える) |
| 売掛金 | 取引先からの未収金(将来入る予定) | △(すぐには使えない) |
| 在庫 | 販売前の商品や原材料などの資産 | ✕(現金化には時間がかかる) |
| 設備投資 | 機械・建物・備品などに変わったお金 | ✕(現金ではない) |
| 借入返済の原資 | 借金の返済に回された分 | ✕(すでに使われている) |
| 引当金(将来の支出) | 退職金や修繕費などに備える積立 | ✕(目的が決まっている) |
理想の雇用の仕組みを考えてみる
かなえ:「なるほど…内部留保は現金だけではないんですね。
私のような小さな事業者にとっても、無理なく続けられて、働く人にも納得してもらえるような雇用仕組みがあれば理想的ですね。」
いち:「ダイアモンドオンラインの記事で、北欧諸国にみられる、ノルディック型の雇用流動提案がありました。
日本にも似たような仕組みがあるので、単なる解雇ではなく、それを発展させていくのも一つの方法なのかもしれませんね。」
安心して失業し、生活費を公費や失業手当で支給されながら、政府支出による「スキルアップ・バウチャー」(リスキル・クーポン)などを活用し、再就職に有利なスキルを、キャリアカウンセリングに基づいて、自らで選択して身につけ、「賃金の高い成長産業」に転職する。
DIAMOND online
かなえ:「日本の職業訓練受講給付金の制度に似ていますね。
生活費を保障したうえで政府が国民のスキルアップを行う、確かに日本に合っていそうです。」
いち:「そうですね。ただし、日本の給付制度は対象者や支給額に制限があるため、北欧のようないわゆる手厚い再就職支援とは少し距離があります。
ノルディック型の路線に乗るならば、もっともっと先に進めていく必要があるでしょう。
なにはともあれ何が最善かは皆で考え続けていかないといけないのでしょうが、近い将来に双方にとって納得感のある雇用制度ができるといいですね。」
労働トラブルは身近なリスク
いち:「ここで労使間トラブルの現状をお話ししておきましょう。
令和5年度全国の総合労働相談件数は1,214,012件で、4年連続で120万件を突破しています。
そのうち、民事上の個別労働関係紛争に関する相談は 266,160件(前年比 2.2%減)と、年間で30〜40万件規模に上ります。」独立行政法人労働政策機構・研修機構リンク
かなえ:「とても多い数字に感じます。
それだけ職場にはトラブルのタネがあるんですね。」
いち:「相談を受けた機関の対応には、助言・相談(労働局長が関与する制度)、あっせん(司法による調停手続き)等があります。
そのなかの“あっせん”に注目すると、合意成立率は約33%、開催されるのは約51% というとても残念な状況になっています。」
かなえ:「多くの会社が、トラブルの解決には至っていない実情があるんですね。」
いち:「一度トラブルが起きれば解決できない例が多くある、ということですね。
労使トラブルになる前に、対策を考えておく必要があるでしょう。
そして、決めたことがちゃんと機能しているか、定期的なチェックを行うことも不可欠です。」
◆労使間トラブルを起こさないための対策の一例◆
・あらかじめ社内ルール整備や相談窓口などを設置しておく
・適切な人事評価とフィードバック
・ハラスメント研修を行う
雇用じゃない人手不足の解消法はある?
かなえ:「何だか人を雇うことが怖くなりますね。
なのでつい、人を雇わずに外注や委託で済ませる方法もあるんじゃないの?って考えてしまうんです。
必要な時だけ頼むならリスクも低そうですし。」
いち:「はい、それもひとつの方法です。
特に起業したばかりで予算に限りがあるなら、外注や委託という選択は現実的な手段です。
ただし、業務の継続性や秘匿性が高い仕事は、やはり正社員の方が適している場合があります。
事業拡大を見据えるなら、どこかで雇用に踏み切る必要が出てくるでしょうね。」
社員と外注の違い一覧表
| 項目 | 雇用(正社員・契約社員) | 外注・委託 |
|---|---|---|
| コスト | 社会保険料や福利厚生費がかかる。 長期的な固定費。 | 必要な時だけ依頼可能。 固定費が少なく変動費中心。 |
| 業務管理 | 勤務時間や業務内容を直接管理しやすい。 | 成果物や納期中心。 作業過程の管理は難しい場合あり。 |
| 継続性・安定性 | 継続的な業務遂行やノウハウ蓄積が期待。 | 契約期間や依頼内容によるが継続性は限定的。 |
| 秘匿性・信頼性 | 社内ルールの適用が可能で、機密保持がしやすい。 | 契約内容により機密保持は可能だがリスクは高い。 |
| 柔軟性 | 人員調整に時間がかかり、柔軟な対応は難しい場合も。 | 必要に応じて依頼量や内容を柔軟に変更可能。 |
| 育成・教育 | 社内で育成や教育ができる。 | 基本的に育成はできない。 |
| 法的責任 | 労働基準法や労災保険などの法的義務が発生。 | 請負契約のため、法的責任は委託先にあることが多い。 |
まとめ
かなえ:「うーん、確かにおっしゃったとおり、会社の将来を考えたらやっぱり雇用は必要だと思います。
事業所を任せられるレベルの社員も欲しいですし、いつかは自分の代わりに動いてくれる信頼できる社員を育てたいって思いがあります。」
いち:「とても前向きな考えですね、素晴らしいと思います。」
かなえ:「でも、まずは外注から始めて、必要に応じて雇用を検討する…っていうのが、私にとっての現実的なステップなのかもしれません。」
いち:「大切なのは、会社の規模・予算・業務内容に応じて最適な人材の確保方法を選ぶこと。
無理なく持続できる仕組みを作っていくことも経営には欠かせない事ですからね。」