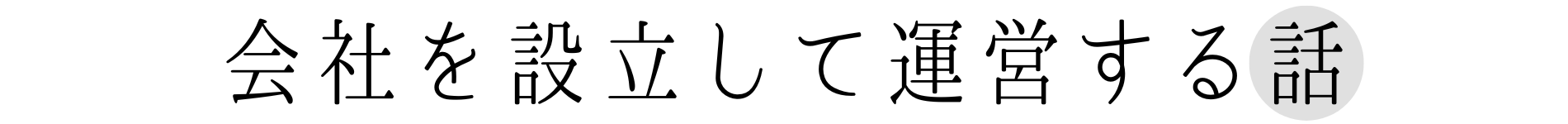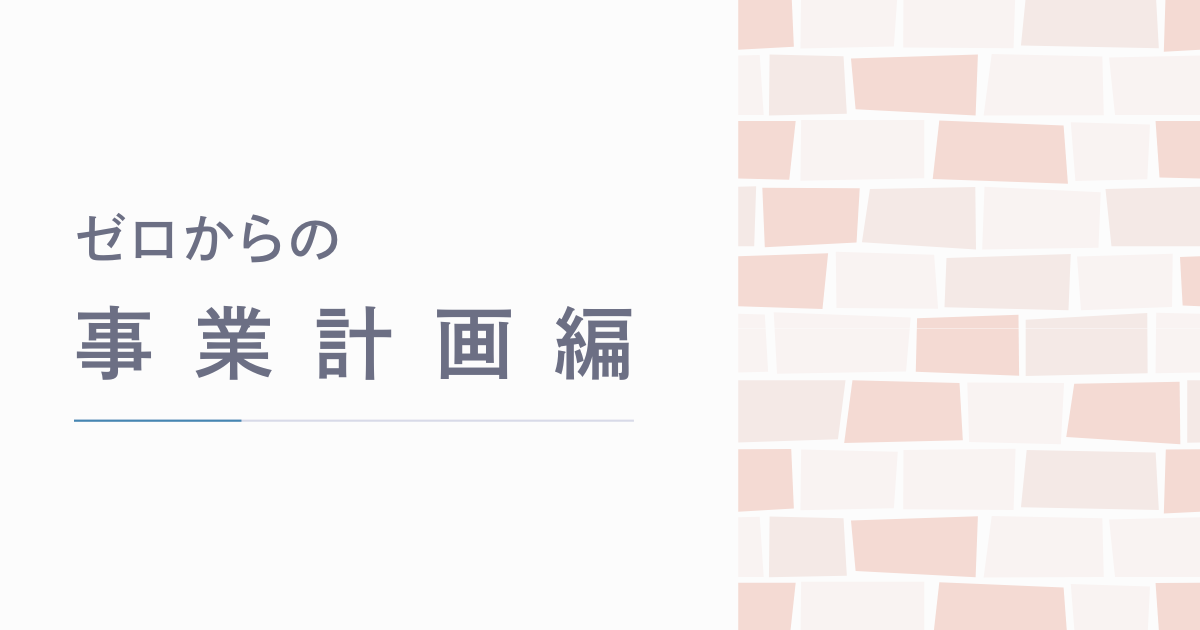登場人物紹介
いち
行政書士事務所所長の行政書士
ゆうき
大学生。会社設立編・はじめての雇用編の相談者かなえの弟。
事業を始めたいと漠然と考えている。
やりたい事業ってどうやって決めたらいいの?
自分の中を掘り下げる「3つの視点」
【ある日、かなえの弟・ゆうきが事務所を訪れる】
ゆうき:「いちさん、僕…将来は姉と同じように起業をしたいなって思っているんです。
でも、具体的に何をやりたいのかは全然決まってなくて。
こんなふわっとした状態で“起業したい”なんて考えちゃダメなんでしょうか?」
いち:「いえいえ全然ダメじゃないですよ!
むしろ、多くの起業家は“何をやるか”より先に“起業したい気持ち”が芽生えるものです。
起業したいという気持ちがあるだけでも十分スタートラインに立っていますよ。」
ゆうき:「少し安心しました。でも漠然と考えているだけでは前に進めないことに気がついたんです。
僕が前に進むためには何をしたらいいかを教えてもらえませんか?」
いち:「それではまず、この“自分の中の3つ”を考えてみましょうか。」
何で起業するのか迷ったら考えよう“自分の中の3つ”
1 自分が“好きなこと”は何か
2 自分の“得意なこと”は何か
3 自分が“関心のあること”は何か
ゆうき:「好きなこと…得意なこと…関心…
うーん、パソコン関係は好きだし、人よりは得意だと思います。
でも、これだ!というほどのこだわりがあるわけじゃなくて…
とにかく、人の役に立って自分が前向きになれる仕事をしてみたいという気持ちなんです。」
いち:「最初から明確じゃなくて大丈夫。
今、好きなこと、得意なことじゃなくてもかまいません。
ただし、漠然と“気づき”を待っているだけではいけません。
“気づき”は急に降ってくるものじゃなく、普段からアンテナを張っている人にだけ集まってくるものですからね。
日常の中からヒントを拾い上げて、“自分の中の3つ”を徐々に言語化していくことが大切です。」
ゆうき:「…もう少し具体的に教えていただけないでしょうか?」
いち:「じゃあ、もう少し深掘りしてみましょう。
たとえばこんなことからも“気づき”が得られると思います。」
・どんな瞬間に楽しいと感じる? →好き・関心
・時間を忘れて没頭した経験は? →好き・関心
・つい調べてしまうトピックは? →好き・関心
・人に褒められたことは? →得意
・逆に、どんな場面でストレスを感じる? →嫌い・不得意
ゆうき:「なるほど。たとえば、人に褒められたことは得意ではあるけど、好きで関心があることに僕自身が気がついていない可能性があるんですね。」
いち:「その通りです。
すでにお気づきだと思いますが、もう一つ大事な視点があるんです。
それは、それは逆も然りということ。
自分の“嫌いなこと”“苦手なこと”にも注目することです。」
ゆうき:「はい、なぜここに“嫌い・不得意”があるんだろうと思っていました。」
いち:「“自分の中の3つ”が事業として成り立つのは理想的ですが、うまく合致しない場合もあります。
ゆうきさんが苦手に感じることは、他の人も同じように苦手な可能性がありますよね。
つまり、そこには“需要”があるかもしれない。
苦手なことを自動化したり、誰かの代わりにやるサービスにしたり、仕組みとして提供すれば立派なビジネスになります。」
ゆうき:「たしかに…!自分の嫌いな作業をお金を払ってでも誰かに頼みたいって思うことってありますね。」
事業にする前に“目的”を言葉にしよう
ゆうき:「自分の“好き・得意・関心”が見えてきた気として、それを事業にするには、どうしたらいいんですか?」
いち:「まず最初にやるべきことは、なぜそれをやりたいのかを人に伝えられるようにすること。
つまり、事業を行う目的を言語化することです。」
ゆうき:「目的を…言語化する、ですか?」
いち:「はい、事業の目的が曖昧なままだと、どれだけ良い事業のアイデアがあっても、
“何をしたい人なのか”が他人に伝わりにくいんです。
目的がはっきりしていると、こんなメリットがあります。
| 事業の目的を明確にするメリット | 内容 |
|---|---|
| 経営判断が一貫する | ・事業の軸ができ、日々の意思決定に迷いが減る ・やるやらないの線引きが明確になる |
| 融資審査で高評価 | 事業の目的が明確だと収益性や継続性が説明しやすく、金融機関からの評価が上がる |
| 家族・協力者の理解を得やすい | 起業の意図を説明しやすく、創業メンバーや家族、取引先から協力を得やすくなる |
| ブランディングの一貫性向上 | ロゴ・商品コンセプト・SNS発信などに統一感が出て、ブランドの芯が強くなる |
| ターゲット顧客が明確になる | 誰のどんな課題を解決する事業なのかが浮き彫りになり、運営やマーケティングが最適化 |
| リスクを把握しやすい | 必要なリソースや許認可等、競合他社などの整理が進み、事前にリスク対策ができる |
| モチベーションの維持 | 困難に直面したときにも“何のために起業したか”を思い出し、再び軸に戻ることができる |
ゆうき:「具体的にはどんな例があるんですか?」
いち:「ゆうきさんはジムに通ったことがありますか?」
ゆうき:「はい、一時期筋トレにはまっていたことがあって通っていたことがあります。」
いち:「では、フィットネス事業を例にしてみましょう。
“子育て中のママさん向けに短時間でできる運動を届けたい”のか、“本格的に体を鍛えたい人にコーチングしたい”のかで、事業設計が全く違いますよね。
目的が曖昧だと誰にも刺さらないサービスになりがちなんです。」
ゆうき:「たしかに!」
いち:「それに、事業はいつも順調とは限りません。
壁にぶつかったとき、“自分はなんのためにこの事業をやっているのか”この軸がしっかりしていれば、迷わずに進めます。」
ゆうき:「表にある、“モチベーションの維持”ですね。
考えてみたら、たしかにどんな有名企業も理念とか、ミッションがすごくはっきりしていますよね。
あれがあるから、何をやっている会社なのか、何を目指しているのかが一瞬で伝わるんですよね。」
いち:「その通りです。人は、目的が明確な会社に安心感や共感を持ちます。
そして、その安心感が選ばれる理由になります。
ブランドが強い企業ほど、目的の言語化が非常に上手なんですよ。」
ゆうき:「ということは…、僕も事業の目的を言葉にできるようになれば、起業の方向性がもっと見えてくるってことでもあるんですね。」
いち:「まさにそこがゆうきさんにとっての初めの一歩になります。
そこが決まると、進むべき道も、選ばれる理由も自然と形になっていきますよ。」
ビジネスとして成立するか?の5つの視点
いち:「次のステップは、そのアイデアが“ビジネスとして本当に成り立つのか?”を確かめることです。
最低でも、この5つは押さえておきましょう。」
1 市場はあるか
▼市場規模はどれくらいか、今後伸びそうか?
2 市場のニーズはあるか
▼「欲しい」と思う人が十分いるサービスなのか?
3 競合相手は誰か
▼自分の強み・弱みを踏まえて比較してみる
4 価格は適正か
▼お客さんが“その価格でも払いたい”と思う金額か?
5 ターゲット層は明確か
▼年齢・職業・ライフスタイルなど、イメージがはっきりしているか
いち:「これらを調べる方法としては、統計データの検証、ネットアンケート、SNSや口コミの分析、競合サイト、店舗の調査などがあります。
ここのステップでのポイントは、“自分が良いと思うだけではビジネスは成立しない”という点です。
その商品やサービスが、“お客さんから見て本当に価値があるのか”を客観的に判断するために必須な工程なんですよ。」
ゆうき:「なるほど……。
実際にニーズがあるかどうかを確かめる必要があるんですね。
内輪で『これ良さそう!』って盛り上がっても、市場がなかったら成り立ちませんもんね。」
いち:「その通りです。
それに調べていくうちに、アイデアの方向性が変わったり、より良い形が見えてくることもあります。
だからここは、調べながら磨く、というイメージですね。」
ビジネスのタネの見つけ方
ゆうき:「うん…。つまり、今までのお話をまとめると、自分に合っていることと、商品力が重なる部分を探す必要がある、ということですね。」
いち:「理想を言えば、以下の3つが重なる場所に、ゆうき君のビジネスのタネがあります。」
1 自分の“好き・得意・関心”があること(もしくは“嫌い・不得意”)
2 自分ができること、または習得できる見込みがあること
3 市場で戦える“商品力(サービス等の無形物含む)があること
ゆうき:「なるほど…でも、どうやってうまく見つけられるでしょうか。
まだ大学生ですから資金も限られていますし、できれば失敗は避けたいです。
効率よく進められるビジネスが見つかればいいんですけど…」
いち:「それはとても現実的な考えですね。
では主要なビジネスモデルにはどのようなものがあるかを確認してみましょうか。」
主要なビジネスモデル一覧表
| ビジネス形態 | 特徴 | メリット | デメリット | 規模拡大のしやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 物販事業(EC・店舗販売・飲食店) | 商品を仕入れて、または加工して、販売する実物ビジネス | ・仕組み化しやすく拡大しやすい ・市場規模が大きい ・初心者でも参入しやすい | ・過剰在庫リスク ・物流・保管コストが発生 ・競争相手が多く、価格競争に巻き込まれやすい | 中〜高(在庫・資金がネック) |
| 情報販売事業(デジタルコンテンツ) | PDF・動画など無形情報を販売 | ・利益率が非常に高い ・在庫不要 ・自動化しやすい | ・信頼性の構築が難しい ・質が低いと炎上リスク(ネット、AIの普及で質ある情報提供難度が上がっている) ・継続収益にはアップデートが必要 | 非常に高(ほぼ無限ともいえる) |
| サービス業(役務提供) | 人が動いて価値を提供するビジネス | ・初期費用が少ない ・スキルを収益化しやすい ・価格競争になりにくい | ・労働集約で時間が不足しやすい ・納期・顧客対応の負担 ・外注化が難しい場合がある | 低〜中(仕組み化できれば向上) |
| マッチング事業(仲介・紹介) | 人や企業をつなぎ報酬を得るモデル | ・利益率が高い ・在庫不要 | ・許認可が必要な場合あり ・必要とする側は集めやすいが、相手を探すことが難しい。 | 低~高(仕組みにより差あり) |
| サブスクリプション事業(定額制) | 継続課金による安定収益モデル | ・継続収益で安定 ・拡大化しやすい ・顧客データを活用しやすい | ・継続的な価値提供が必要 ・解約率管理が必須 ・初期は赤字になりやすい | 高(顧客の継続率向上が必須) |
| 広告モデル事業(メディア運営) | PVや視聴数に応じて広告収入を得る | ・在庫不要 ・自動収益化しやすい ・小規模で始められる | ・収益化まで時間がかかる ・アルゴリズム依存 ・収益が不安定 | 中〜高(ヒットすれば大きな収入が見込める) |
| フランチャイズ事業(FC加盟) | 本部のブランド・仕組みを借りて運営 | ・初心者でも参入しやすい ・ブランド力を活用できる ・集客が比較的安定 | ・ロイヤリティ負担 ・自由度が低い ・初期投資が高額 | ・本部 中~高(複数店舗化で拡大) ・FC加盟店 低(規模拡大は限定的) |
ブルーオーシャンを狙おう
ゆうき:「僕のような素人だと、起業といえば物販事業を真っ先に思い浮かべますけど、資金が必要だし、競争相手が多いとなるとなかなか簡単ではありませんね。」
いち:「そうですね。どのビジネスも競争相手がいない事業に参入するに越したことはないと思います。」
ゆうき:「いわゆるブルーオーシャンというやつですね。」
いち:「はい、特に大手企業の多くが参入してレッドオーシャンとなっている事業は避けた方が無難です。
特に、生活必需品は大手との価格競争にも巻き込まれてしまうので、資金力のない新規参入のハードルはかなり高いといえるでしょう。
創業時は初期投資が小さいビジネスモデルを意識するといいですよ。
たとえば、PCを使って、継続的な収入が見込めるサブスクリプションや、ネット上で完結する情報提供やサービス系の事業などが、資金力やリソースの限られた起業家に向いています。」
ゆうき:「表にもありましたね。何か事例ってありますか?あまりピンとこないので…」
いち:「たとえば、SaaS(Software as a Service)を提供している企業の商品が参考になると思います。
アップデートで内容を時々の状況で変えられたり、内容を顧客に合わせられたりとカスタマイズ性が高く、継続収入が見込めるモデルが多くあります。
有名なものではこんなサービスを聞いたことがありませんか?
ビジネス文書(Microsoft 365・Google Workspaceなど)
デザイン制作(Canvaなど)
ファイル共有(Dropboxなど)
クラウド会計(マネーフォワードクラウドなど)
生成AIを利用したビジネス(ChatGPTなど)
実際にサービスを使ってみて、“自分だったらどう改善するか?”という視点を持つこともきっといい訓練になります。」
日本で事業を始めるときの“信頼”と“ルール”
ゆうき:「うん…。なんとなく方向性が見えてきた気がします。
あと、実際に事業を始めるとなったら、他に気をつけることってありますか?」
いち:「はい、大切なポイントがあります。
日本の商慣習や、コンプライアンスへの意識も、忘れずに持っておきましょう。」
ゆうき:「商慣習って、たとえばどんなことですか?」
いち:「日本では、商品そのものの品質だけでなく、“信頼できる会社かどうか”が非常に重視されます。
品質の安定性はもちろん、サービスの丁寧さや対応のスピードも同様に評価の対象になる傾向があります。
口コミや紹介で仕事が広がることも多いので、一つ一つの取引を丁寧に積み重ねる姿勢が求められるんですよ。」
ゆうき:「たしかに覚えがありますね。
いわゆる“信用第一”の意識が大切ということなんですね。」
いち:「“信用第一”に加えて、最近はコンプライアンス、つまり法令順守への意識も非常に重要になっています。
国の許認可等が必要な事業で必要な手続きをしていないと違法営業になってしまいますが、これは誰が教えてくれるでもなく、自分自身で調べないといけません。
知らずに思わぬ法令違反を犯してしまうこともあるので、事前に必要な手続きや法律等のルールを確認しておくことも大切なんですよ。」
ゆうき:「見落としがちなことですから気を付けないといけませんね。
信用第一やコンプライアンスの意識は、日本に限らず海外を視野に入れた場合にも役に立ちそうです。」
まとめ|実際に事業を始めた際の注意点も
ゆうき:「今回のお話を自分なりにまとめてみるとこんな感じでしょうか。
今やりたいことがない
↓
自分の内面を掘り下げてみる
↓
行動して興味のあることを見つける
↓
世の中のニーズと接点があるか検証
整理していて感じましたけど…、一朝一夕にはいかなそうですね。
まずはあせらずにひとつひとつやっていこうと思います。」
いち:「はい、焦らずに向き合うことが第一歩です。
SOFTBANKグループ創業者の孫正義さんは毎日何個ものアイデアを書きだす、ということをル-ティーンにしていたようですよ。
ゆうきさんは人が困っていることや困っていそうなことを毎日いくつか書き出す、なんてことをやってみてもいいかもしれませんね、数字は具体的にしておいた方がいいですよ。」
ゆうき:「今日からやってみたいと思います!」
いち:「さてひと段落つきましたが、ゆうきさんは開業資金についての話は、興味がありませんか?」
ゆうき:「実はそれが一番気になっていました。
ぜひ教えてください!」