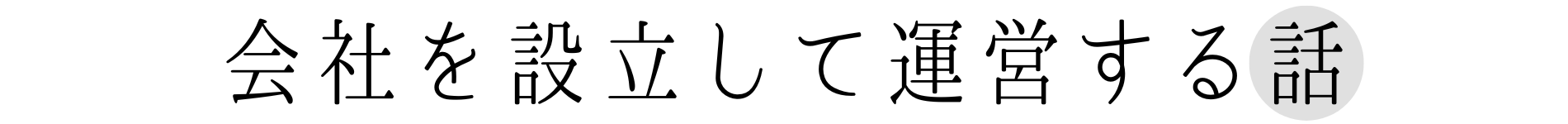登場人物紹介
いち
行政書士事務所所長の行政書士
かなえ
起業の夢を無事かなえたWEBデザイン会社経営の女性 会社設立編はこちら
かなえ雇用を考える
かなえ:「こんにちは、いちさん!お久しぶりです!」
いち:「お久しぶりですね、かなえさん。会社のほうは順調ですか?」
かなえ:「はい、おかげさまで!
最近はウェブサイトからの問い合わせや、お客様の紹介も増えてきて、だいぶ忙しくなってきたんですよ。」
いち:「それは素晴らしいです!かなえさんの努力の成果ですね。」
かなえ:「ありがとうございます。でも、忙しくなるのはうれしいんですけど、さすがに一人では手が回らなくなってきて…。
そろそろ誰かを雇った方がいいのかなって考えてるんです。
でも人を雇うことには不安もあって…人の生活に責任を持たなければならなくなるわけですし。
人を雇った方がいいのか、それともこのまま続けた方がいいのか迷っています。」
いち:「なるほど、人を雇うことを検討し始めたんですね。
たしかに“雇用”ってなると、一気に責任の重さを感じますよね。」
かなえ:「そうなんです。失敗したらどうしようとか、手続きも難しそうで…
なんとなく“ハードルが高い”イメージがあって、踏み出せずにいるんですよ。」
いち:「その気持ち、よくわかります。
雇用は会社設立の次に大きなステップですから、不安になるのは当然ですよ。」
かなえ:「でも、ちゃんと仕組みを知れば不安も減るかなと思って。
いちさん、雇用の基本から教えてもらえますか?」
いち:「もちろんです。
では、はじめて人を雇うときに知っておくべきポイントを、順を追って説明していきましょう。」
人を雇う前に知っておくべきこと
雇用は経営上の重要な判断。責任や覚悟も必要
いち:「経営者の方なら、きっと日頃から意識していることだと思いますが──
まずは、人を雇う前の“心がまえ”からお話ししたいと思います。」
かなえ:「大事なところですね。ぜひ聞かせてください。」
いち:「人を雇うというのは、当たり前のようでいて、とても大きな責任を伴います。
たとえば、生活できるだけの給与をしっかり支払うこと。
そして、育成や公正な評価の仕組みを整えて、安心して働ける環境をつくることも大切です。
それは従業員のためだけではなく、最終的には会社の成長や利益にもつながっていくんですよ。」
労働法やマイナンバー法など、最低限知っておくべき法律
いち:「それから、人を雇ううえで欠かせないのが“法律の知識”です。
雇用に関わる主な法律には、次のようなものがあります。」
| 法律名 | 趣旨 |
| 労働基準法 1947年9月施行 | 働く人の最低限のルールを決めた法律。労働時間や残業代、休日、解雇などについて決まっています。 |
| 男女雇用機会均等法 1986年4月施行 | 採用や昇進、給与などで、性別による差別をしてはいけないという法律です。 ※当初は労働基準法の一部だったが、1985年に独立法化 |
| 労働契約法 2008年3月施行 | 雇うときの契約内容のルールをまとめた法律で、解雇や試用期間のルールも含まれます。 |
| 個別労働紛争解決促進法 2001年10月施行 | 労働者とのトラブルが起きたとき、会社と従業員の間に労働局などが入り、解決をサポートしてくれる仕組みの根拠になる法律です。 |
| 個人情報保護法 2005年4月施行 | 従業員の履歴書や健康情報など、個人情報を適切に管理しないといけないという法律です。 ※施行日は全章が対象になった施行日 ※全事業者対象となったのは2015年改正以降(以前は一部事業者のみ適用) |
| マイナンバー法 2016年1月施行 | 従業員のマイナンバーを取り扱うときに、特に慎重な管理をするよう求める法律です。 |
かなえ:「6つもあるんですか! 思ったより多いですね。
それぞれの内容はなんとなく分かりましたけど……正直、細かい部分まで理解する自信はなくて。
こういうのって、専門家に全部任せても大丈夫なんでしょうか?」
いち:「専門家に相談するのはとても良いことですが、すべてを任せきりにするのはおすすめできません。
労働条件を決めたり、実際に従業員と接するのは経営者自身ですからね。
最低限の法律知識を持っておくことは、会社を守るうえでも大切なんです。
それに、基本を理解したうえで専門家の意見を聞くのと、何も知らずに聞くのとでは、理解の深さが全然違います。」
かなえ:「うーん、なるほど……たしかにそうですね。
最近はコンプライアンス(法令順守)にも厳しいですし、経営者としてちゃんと勉強しなきゃいけませんね!」
法律違反が招くリスクとマイナンバー管理の注意点
いち:「法律知識を付け、きちんと体制を整えておくことは経営者自身を守ることにも繋がり、とても大切なことですが、基本的には“故意ではない”違反については、いきなり罰を受けるようなケースは少ないんですよ。」
かなえ:「そうなんですね。それを聞いて少し安心しました!」
いち:「とはいえ、どんなリスクがあるのかを知っておくことも大切です。
たとえば、会社で預かる従業員のマイナンバーの管理について、一つ例を挙げてみましょう。」
マイナンバーの取り扱いを怠るとどうなるか
マイナンバーは“特定個人情報”として、通常の個人情報よりも厳格な管理が求められます。
担当者が意図的に漏えいしたり、目的外に利用した場合などには、最長4年の懲役または200万円以下の罰金という重い刑事罰が科される可能性があります。
また、会社として管理体制に不備があり、経営者がその責任を怠っていたと判断された場合は、経営者自身が責任を問われることもあります。
かなえ:「なるほど……やっぱり知識を持って、しっかり管理体制を整えることが大事なんですね。
こういうのって、忙しいとつい後回しにしてしまいそうですけど、法令順守は会社の信用にも関わりますもんね。」
いち:「そうですね。知らなかったばかりに法律違反になってしまったり、従業員とのトラブルにつながることもあります。
そんなことで、せっかく積み上げてきた会社の信頼を失うのは本当にもったいないことですよね。」
雇用にともなう主なリスクとは?
かなえ:「人を雇えば、仕事がスムーズに回って売り上げも伸びる――ついそう考えてしまうんですけど…やっぱり、人を雇うことにもリスクってあるんですよね?」
いち:「ええ、もちろんあります。雇用には“人”に関わるリスクがつきものです。
特に小規模な会社では、一人ひとりの働きが経営に直結しますから、人材の質がより重要になってきます。
でも日本の法律では、たとえ思ったような成果が出なかったとしても、簡単に解雇することはできません。
解雇をするには、いくつかの厳しい要件を満たさなければならず、それを欠いたまま行えば裁判で“不当解雇”と認定される可能性があります。
もし不当解雇と判断されれば、数百万円単位の支払いを命じられるケースもあるんですよ。」
かなえ:「えっ……そんなにですか?
小さい会社だと、それだけで経営が傾くこともありますね。」
主な雇用リスクの一覧|不当解雇・情報漏えいなど
かなえ:「罰則の重さは想像以上ですね。
具体的には、雇用にはどんなリスクが考えられるんでしょうか?
いち:「雇用のリスクとして考えられるものはいくつもあります。
代表的なものを整理してみましょう。」
| リスクの種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 法的リスク | ・不当解雇による訴訟リスク ・ハラスメント対応の不備 ・労災認定による補償責任 |
| 経済的リスク | ・人件費の固定化と負担増 ・ミスマッチによる採用や早期退職による教育コストの損失 |
| 組織運営リスク | ・職場の人間関係の悪化 ・マネジメント負荷の増大 ・社内ルール未整備による混乱 |
| 人的リスク | ・情報漏えいや内部不正(SNSリスク含む) ・急な退職や無断欠勤 ・メンタル不調による長期休職 |
| 社会的リスク | ・SNSやメディアでの評判悪化 ・コンプライアンス違反の露呈 ・企業イメージの毀損 |
リスクを最小限にするために経営者ができること
かなえ:「どれも現実に起こりそうな話ばかりですね…。
従業員として働いていたときはありがたい仕組みだったのに、経営者の立場になるとリスクに見えてくるのが不思議です。」
いち:「まさにそのとおりです。
中でも“経済的リスク”は特に重いですね。
たとえば、従業員がメンタル不調で長期休職になった場合、業務の負担や人件費の面で影響が大きくなります。」
かなえ:「確かに…。でも従業員の立場からすれば、安心して働ける環境がないと不安になりますよね。
体調や家庭の事情で、どうしても仕事を休まざるを得ないこともありますし。」
いち:「おっしゃるとおりです。
だからこそ、そうした“やむを得ない事情”に備える仕組みを整えておくことが大切なんです。
たとえば、休職や働き方に関するルールを明確にしておくこと。
それに、業務を一人だけに任せず、他の人でも対応できる体制をつくることも重要ですね。
つまり、リスクを前提とした備えを経営の一部にしておくことがポイントです。」
かなえ:「なるほど。制度や仕組みを作っておけば、トラブルを防ぐことにもつながるんですね。
でも…もし従業員が一人しかいない場合は、どうしても頼らざるを得なくなっちゃいますよね。その場合はどうすれば?」
いち:「確かに、少人数の会社ではそうなりがちですね。
ただ、“仕方がない”では済まされないケースもあります。
だからこそ、採用の段階での見極めと、入社後のフォロー体制がとても大切なんです。
さらに、業務のマニュアル化を進めておくことで、急な休職や退職があっても混乱を最小限に抑えることができますよ。」
人を雇うとどれくらいお金がかかるのか?
社会保険料や設備投資などの固定費用
かなえ:「人を雇ったときに、どんなお金がかかるのかも気になりますね。」
いち:「実際には、雇用に関わる費用は思っているより多いんです。
主なものを整理してみましょう。」
| 対象 | 具体例 | 備考 |
|---|---|---|
| 給与 | 会社の給与規定による | 全額会社負担 |
| 社会保険料(法定) | ・健康保険料(協会けんぽ等) ・厚生年金保険料 ・雇用保険料 ・労災保険料 ・介護保険料(40歳以上) | 健康保険・厚生年金:会社・従業員で折半(50%ずつ) 雇用保険:従業員賃金 × 保険料率 労災保険:会社が全額負担 |
| 労働環境の整備費 | ・PC、机、椅子などの備品 ・電気・ネット環境などのインフラ整備 ・労働条件通知書や就業規則などの書類整備 ・勤怠・人事管理システム | |
| 研修費用 | ・社内研修・外部研修費 ・教育資料やマニュアルの作成費 | |
| 福利厚生費(法定外) | ・交通費・通勤手当 ・健康診断(年1回は法定義務) ・慶弔見舞金、社内イベント ・資格取得支援など |
福利厚生や研修など、見落としがちな変動費用
かなえ:「給与だけじゃなくて、こんなにいろいろなお金がかかるんですね。」
いち:「そうなんです。法律で義務づけられていない項目もありますが、実際には必要になることが多いです。
“給与以外にも多くの費用が発生する”という前提で、しっかり資金計画を立てておくことが大切なんですよ。」
まとめ|リスクとコストを理解して、前向きな雇用判断を
かなえ:「うーん…やっぱり人を雇うって、覚悟がいりますね。
でも、リスクや費用のことを知ったうえで準備できるなら、むやみに怖がらなくてもいい気がします。」
いち:「そうですね。
リスクやコストは避けられませんが、“雇用=負担”と決めつけず、どう活かすかを考えられる経営者こそ、信頼される組織を育てていけるんだと思います。
簡単ではありませんが、それが経営の面白さでもありますね。
では次回は、実際に人を雇うまでの具体的な流れを見ていきましょう。」
かなえ:「はい!楽しみにしています。」