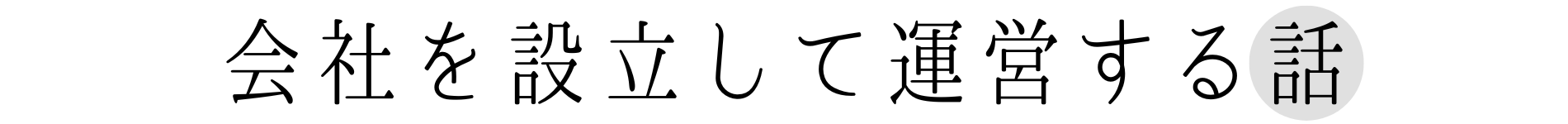人を雇うときの基本ステップと準備
かなえ:「前回のお話で、雇用には責任やリスク、そして費用も伴うことがよく分かりました。
やっぱり、人を雇う前にはしっかりと準備が必要なんですね。
今回は、人を雇うまでの具体的な手順を教えていただけるんですよね?」
いち:「はい、そうです。今回は実際に人を雇うときの全体の流れを、ステップごとに整理して見ていきましょう。
全体像をつかんでおくと、今どの段階にいて何をすべきかが明確になりますよ。」
雇用の5つのステップ
step1. 労働条件の決定
step2. 従業員の募集・選定
step3. 労働契約の締結
step4. 社会保険等の届け出
step5. 社員の退職時に必要な手続きと会社の対応
いち:「それでは、各stepを順を追って説明していきましょう。
今回はstep1 労働条件の決定と、step2 従業員の募集・選定を説明します。」
Step1:雇用前に必要な“労働条件”の整理
いち:「まず最初に、労働条件をきちんと決めておくことが大切です。
そのときには、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできる“労働条件通知書”を使うと、抜け漏れがなく安心ですよ。
労働条件通知書は、労働基準法で従業員に必ず明示することが義務付けられている重要な書類ですから、わざわざ一から作る手間も省けます。
ただし、内容に虚偽があったり、差別的な表現を入れると、職業安定法違反になってしまうので注意してください。」
労働条件通知書に必ず書く項目|絶対的明示事項
いち:「労働条件通知書には必ず明記しなければならない、以下の項目があります。」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 労働契約の期間 | 契約が有期の場合は期間や更新の有無、更新基準を記載 |
| 2 就業の場所・業務の内容 | どこで・どんな仕事をするのか明記 |
| 3 始業・終業の時刻、休憩・休日等 | 所定労働時間、休憩時間、休日、交替制の有無など |
| 4 賃金の決定・支払い方法 | 基本給、手当、支給日、締日、控除など |
| 5 退職に関する事項 | 解雇の事由や手続き、自己都合退職の扱いなど |
必要に応じて記載する項目|相対的明示事項
いち:「以下は必要に応じて記載をする相対的明示事項です。」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 昇給 | 昇給の有無や基準、実施時期 |
| 退職手当 | 支給条件、計算方法など |
| 賞与 | 支給の有無、支給時期や計算基準 |
| 就業規則 | 適用される就業規則の有無と名称 |
| 表彰・制裁 | 懲戒規定や表彰制度など |
| 安全衛生等 | 災害補償、業務外の疾病補償、安全衛生の取組など |
※2024年法改正で追加された記載ルール
| 項目 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 就業場所・業務の変更範囲 | 転勤や異動の可能性がある範囲を記載 | すべての労働者 |
| 有期契約の更新上限 | 更新の有無、更新回数、通算契約期間など | 有期契約労働者 |
| 無期転換申込機会と条件 | 無期転換の申込時期と転換後の労働条件 | 有期契約労働者 |


時間外労働に必要な“36(サブロク)協定”
いち:「法定労働時間は、原則として1日8時間、週40時間までというのは、みんながよく知っているルールですよね。
また、時間外労働の上限は原則として、月45時間、年360時間までと決まっています。」
かなえ:「はい、学校で習った覚えがあります。」
いち:「でも、実際にはそれを超えて残業させることもあります。
その場合は、従業員と書面で合意して、労働基準監督署に届け出る必要があります。
この仕組みを“36(サブロク)協定”と呼ぶんですよ。」
かなえ:「えっ、法律で上限が決まっているのに、36協定を結べば残業させられるんですか?
従業員としては、断りにくいですよね…。」
いち:「そこは少し誤解があります。36協定は、会社が好き勝手に残業させるための“免罪符”では決してありません。
労働基準法36条に基づき、労働者代表と会社が合意した時間外労働の上限や条件を明示し、その範囲内でのみ時間外労働が認められる仕組みです。
ですので、協定を結んでも合意の上限を超えた残業は違法になります。
届け出や合意を行うことで、むしろ労働者を守る役割があるんですよ。」
かなえ:「なるほど…。でもやっぱり、従業員からすると断りにくい面もありますね。」
いち:「そうですね。法律の趣旨はお話しした通りですが、実際には雇用側に都合よく使われている面もあります。
近年の法改正で改善はされていますが、36協定の上限や運用にはまだ議論の余地があります。」
募集方法と面接のポイント
求人広告は何を選んだらいいの?
かなえ:「従業員を募集するときって、何を参考に考えたらいいんでしょうか?」
いち:「募集方法はいろいろあります。
ハローワーク、民間の求人サイト、SNS、知人からの紹介などですね。
最近は専門職向けの求人サイトも多いので、特定のスキルを持った人を探す場合は、こうしたサイトを活用するのがおすすめです。」
かなえ:「うちのようなWEBビジネスだと、専門職向けのサイトが向いているのかもしれませんね。
ハローワークは、多くの人に求人を検討してもらえるイメージがありますけど、実際はどうなんですか?」
いち:「ハローワークは、掲載が無料で認知度も高く、地域密着の求人を中心に幅広く使われています。
なので、今でも有力な選択肢の一つですね。
ただし、求人件数の統計は民間サイトと単純比較できず、最近は企業の利用件数や紹介件数が減少傾向にあるという調査もあります。
今は、求人サイトやSNSなど複数の方法を併用するのが一般的です。
かなえさんも、気になる方法を組み合わせて試してみるといいですよ。」
採用面接で気をつけること
いち:「次は、面接のときに注意すべきポイントをお話ししましょう。
採用面接では、応募者の適性や能力に直接関係のない質問は、原則として避ける必要があります。
厚生労働省の『公正な採用選考のためのガイドライン』でも、仕事に関係のない事項を聞くことは不公正な選考につながると明示されています。」
かなえ:「性別や家族のこと、結婚や出産の予定なんかは聞かない方がいいって聞いたことがあります。」
いち:「そうですね。具体的には、配偶者の有無や結婚・出産の予定、宗教や支持政党、家族の介護や扶養の状況などは聞いてはいけません。
これらは仕事の能力とは関係がなく、質問すると差別やプライバシー侵害と受け取られる可能性があります。」
かなえ:「うっかり聞いてしまいそうな内容ですね。面接官がルールを知らず、SNSで炎上するケースもありますし…。」
いち:「そうです。法律上、会社に面接官への教育や指導の義務は明記されていませんが、トラブルを避けるためには事前にしっかり対応しておくことが大切です。
ガイドラインに沿った対応を徹底しないと、法律の趣旨に反する採用差別とみなされ、企業の信頼や評判を損なう危険があります。」
採用合否の判断のコツは?
かなえ:「私、以前会社で面接官をやったことがあるんですが、どうしても印象で判断しがちで…。
面接にはあまり自信がないんです。
面接のコツのようなものはありますか?」
いち:「大切なのは、質問の幅を広げることと、判断基準を明確にすることです。
先入観や思い込みで決めつけずに、“会社の採用基準に沿って客観的に判断すること”がポイントですよ。
つまり、個人的な感覚に頼らず、会社が求める能力や適性に合うかどうかを軸にすると判断しやすくなります。」
かなえ:「なるほど…。多面的な質問と基準の明確化、これを意識してみます。」
いち:「では次回は、step3の労働契約の締結について解説しましょう!」
かなえ:「はい、よろしくお願いします!」