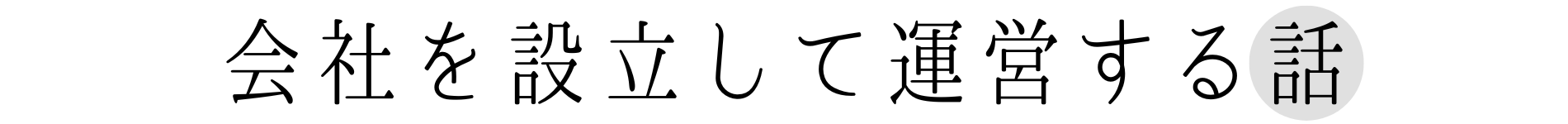株式会社設立のメリット・デメリットとは?
いち:「では、さっそく株式会社設立のメリットとデメリットから説明を始めましょう。」
株式会社にする7つのメリット
いち:「会社を設立するメリットとして考えられるのは、この7つです。」
◆株式会社にする7つのメリット◆
1 有限責任
2 資金調達が容易
3 リスクの分散
4 継続性と事業承継のしやすさ
5 信頼性と認知度の向上
6 経費計上の幅広さと節税効果
7 社会保険への加入
1.有限責任|株式会社は出資額以上の責任なし
株主の法的責任が投資した資本の範囲に限定されます。
会社の負債が発生した場合でも、株主は自身の出資額以上の責任を負いません。
2.資金調達が容易|株式発行・融資に強い株式会社の資金調達力
株式会社は株式を発行することで資金を調達できるため、金融機関からの融資に頼らなくても企業活動を維持、発展させやすいです。
また、他の事業形態よりも金融機関からの融資を受けやすいといわれています。
3.リスクの分散|出資者を増やしてリスク分散
株式会社は、多数の株主を持つことができ、これにより個人のリスクを分散できます。
4.継続性と事業承継のしやすさ|経営者が変わっても会社は続く
株式会社は法人格を持つため、経営者が亡くなったり、株主や役員が入れ替わったとしても会社そのものは存続します。
さらに、株式を譲渡することで会社の所有権を円滑に移転できるため、事業承継の手続きが比較的スムーズに進められます。
その結果、会社として培った信用や取引関係を維持したまま事業を継続しやすいという大きなメリットがあります。
5.信頼性と認知度の向上|取引や採用に有利
株式会社は法人格を持ち、法的に整備された形態であるため、社会的な認知度が高く、取引先や顧客からの信頼性を得やすいという特徴があります。
この信頼性によって、優秀な人材が応募してきやすくなり、定着しやすくなるなど、事業運営におけるメリットが期待できます。
6.経費計上の幅広さと節税|株式会社の経費と税制メリット
個人事業主よりも、経費として認められる範囲が広くなります。
たとえば、経営者自身の役員報酬を損金(経費)として計上できたり、事業に関連する支出であれば交際費や福利厚生費なども経費にできるため、課税所得を抑えることができます。
結果として節税がしやすくなり、利益を増やす工夫がしやすくなります。
7.社会保険加入による従業員・経営者のメリット|厚生年金・手当も充実
株式会社には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。
社会保険への加入は、従業員だけでなく経営者自身にとっても、大きなメリットがあります。
健康保険には、国民健康保険にはない傷病手当金や出産手当金といった保障があり、病気や出産による収入減を補う仕組みが整っています。
また、厚生年金に加入することで、将来受け取れる年金額が国民年金のみの場合より増えるため、退職後の生活設計を安定させやすくなります。
一方で、個人事業主は厚生年金に直接加入できないため、将来の年金受給額が少なくなったり、加給年金・遺族厚生年金・障害厚生年金といった厚生年金特有の給付を受けられないという違いがあります。
社会保険は個人事業主よりも株式会社の方がお得
かなえ:「個人事業者の年金受給が国民年金だけになるというのは不安がありますね。」
いち:「会社に所属していると、将来受給できる年金は国民年金に加えて厚生年金がありますので、大きな違いになりますよね。
ただし、個人事業主には老後に備える仕組みがないわけではなく、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの代替策があります。」
かなえ:「個人事業主は国民年金の他に、個人年金で備える必要があるってことなんですね。
国民年金だけでは不安がありますもんね。」
いち:「はい、人によるとは思いますがその方が安心ですね。
ただし、iDeCoは投資リスクも伴いますし、企業が半分負担してくれる厚生年金と比べると掛け金総額や給付の安定性で劣る面もあります。
厚生年金の完全な代替となるものではなく、“タイプが違うものだ”ということは覚えておいた方がいいのかもしれません。」
かなえ:「はい、たしかにそうですね。
確定拠出年金は、専門家に資金運用をお願いするものですから、導入の際には最低限の勉強が必要だと思います。」
“経費=損?”会社の経費と節税の関係
いち:「メリットの一つである、社会保険料は会社の経費にできる、というのも嬉しいところなんですよ。
個人事業では国民健康保険料を経費にすることはできませんから。」
かなえ:「経費が増えるのは会社にとっていいことなんですか?
逆にマイナスなんじゃ…と思ってしまったんですが…」
いち:「経費が増えるというとマイナスイメージがありますよね。
でも正確には、運営に必要な出費が経費として計上できるということなんです。
経費が掛かって会社の利益が減れば、会社の利益に掛かる税金が減る可能性がでてきます。
つまり、個人事業では経費にできないものが会社では経費にできる、というのは会社化の大きなメリットの一つなんですよ。」
かなえ:「なるほど…、経費が多くなれば納める税金が減るかもしれない、ということなんですね。
経費にできるものが多い方がいい理由は分かりました。」
いち:「では次に、デメリットについての説明をしましょう。」
株式会社のデメリットとは?|3つのデメリット
◆株式会社にするデメリット◆
1 設立・維持コストの増加
2 情報公開の必要性
3 経営の自由の制限
1.設立・維持コストの増加|会社設立にはお金が必要
・株式会社を設立するには定款認証料(上限5万円)・印紙税4万円+登録免許税(最低15万円)+その他(証明書など)で、合計で24、5万円程度は掛かるのが一般的です。
・利益が一定以上ない段階では、法人の方が税負担が重くなることがあります。
・難解な法人税の計算に対応するため税理士に依頼する外注費や、法的義務である提出書類が増えることで雇用の必要が出てきたりと、維持運営コストが高くなります。
・法人である株式会社は法人税、法人事業税、法人住民税を支払わなければなりません。
売り上げがなければ、法人税と法人事業税は支払わなくてもいいのですが、売り上げがなくても、法人住民税の均等割分(最低額年7万円)は支払いが必要な固定費になります。
2.情報公開の必要性|株式会社は情報開示が義務
株式会社は情報開示が求められます。
会社の財務状況や業績などの情報が公開されるため、競合他社等によって情報の利用をされるリスクがあります。
3.経営の自由の制限|自由に動けない定款や株主の制約
・原則として、定款に記載された事業目的の範囲内でしか事業を行えず、目的外の事業を始めるには手順を踏んだ定款変更が必要です。
・株主が複数の場合には、議決権のある株主の意向によって経営方針や重要な決定に影響を受ける可能性があります。
・株式会社ではたとえ経営者であっても会社のお金を自由に使うことはできません。
不適切な資金の流用は法令違反とされ、ときに刑事罰の対象となります。
制約はマイナス?それでも会社が選ばれる理由とは
かなえ:「ルール守らないといけなかったり、会社のお金を好きなように使えない、というのは会社にとってはむしろメリットのようにも思えますね。」
いち:「確かにおっしゃる通りで、デメリットには挙げましたが、株式会社は法による制約が多いので、信頼をされるという面があります。
明らかなデメリットといえるのは、コストが掛かることだけなのかもしれませんね。」
かなえ:「会社って誰にでも共通する枠組みがあるので信頼が得られるんですね。
個人事業を始めるまでのハードルの低さには魅力を感じますけど、やっぱり取引先の見る目や将来の資金調達のことを考えると、ちょっと不安が残ります。
でも、株式会社の“コストが掛かる”というのはとても大きなデメリットなので…ここをもっと聞いてみたいです。
個人事業と会社の税金の違いも気になります。
個人事業に課せられる税金と株式会社の税金、どれだけ違うのかを教えていただけませんか?」
いち:「税金は起業家にとってとても気になるところですよね!
では次回は、個人事業と株式会社双方に課せられる税金について比較してみましょう。
それに、“どのくらいの所得が見込めれば会社の設立を考えるきっかけになるのか”、これも気になりませんか?
そこも併せて解説しましょう。」