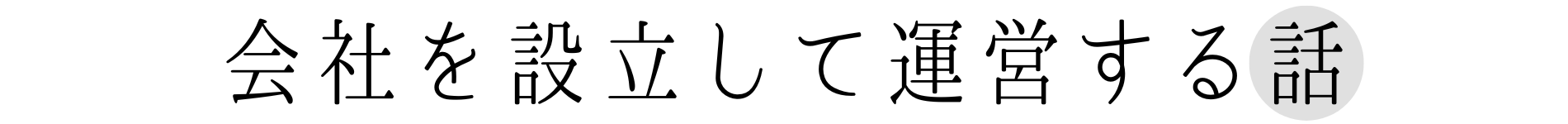会社設立後に必要な手続きとは?
かなえ:「案外すんなりと法人口座の審査に通りました!
すごくほっとしています。」
いち:「スムーズに進んでよかったですね!
かなえさんはきちんと段取りを踏んで進めていましたから大丈夫だとは思っていました。
それでは、最後に会社設立後にやることについて説明しましょう。
登記が完了したからといって、自動的に法務局から各行政機関へ会社の設立が知らされるわけではないので、自分で各種届け出をしていかなければならないんです。」
かなえ:「はい!もうひとがんばりですね!」
提出が義務付けられている書類
いち:「会社設立後に、行政機関へ提出が義務付けられている書類がありますので、そちらから説明しましょう。
全部で5つあって、それぞれに異なった提出期限がありますので注意が必要です。
期限内に提出しなくとも罰則はありませんが、届け出をしないことで優遇措置が受けられなくなる可能性があります。」
税務署へ提出する義務書類|法人設立届出書など
法人設立届出書
【期限】設立日から2か月以内
【提出先】会社所在地所轄の税務署
【テンプレート】あり 国税庁
【添付書類】定款のコピー・株主名簿・法人事業概況説明書
いち:「国税課税のために必要な書類です。
2017年4月以降、国税庁宛の法人設立届出書には登記事項証明書が不要になりました。
後述しますが、“地方自治体にも”法人設立届出書の提出が必要な場合があります。
ややこしいので注意が必要です。」
自治体へ提出する義務書類|事業開始等申告書など
事業開始等申告書(自治体によって名称が異なる場合があり)
【期限】設立日から15日〜1か月以内 ※自治体により異なる
【提出先】都道府県税事務所、市区町村税務課など
【テンプレート】自治体により異なる
【添付書類】定款のコピー・登記事項証明書など ※自治体により異なる
いち:「地方税の課税のために必要な書類です。
事業を始めるには、税務署のみならず都道府県や市区町村にも法人設立届出書の提出が必要です。
また、自治体によっては法人設立届出書と事業開始等申告書が一体になっていて、一方の提出で足りる場合があります。
どのようなシステムになっているかは、自身の会社がある自治体に確認をしましょう。」
給与支払事務所等の開設届出書
【期限】設立日から15日〜1か月以内
【提出先】会社所在地所轄の税務署
【テンプレート】:あり 国税庁
【添付書類】定款のコピー・登記事項証明書など
いち:「従業員がおらず、役員報酬のみの場合でも提出義務があります。」
年金事務所へ提出する義務書類|健康保険・厚生年金新規適用届など
健康保険・厚生年金新規適用届
【期限】法人設立後5日以内
【提出先】会社所在地所轄の年金事務所
【テンプレート】あり 日本年金機構
【添付書類】登記事項証明書、賃金台帳など
いち:「役員が一人の場合でも、役員報酬を支払っていれば(報酬があれば)、株式会社には健康保険と厚生年金に加入する義務があります。」※社会保険の適用除外となるケースあり(75歳以上など)
被保険者資格取得書
【期限】報酬を受け取り始めた日から5日以内
【提出先】会社所在地所轄の年金事務所
【テンプレート】あり 日本年金機構
いち:「健康保険、厚生年金の資格を取得した全員分を個別に提出します。
従業員を雇用した場合には、その都度被保険者資格取得書が必要になります。」
届出義務書類まとめ表
| 名称 | 義務か任意か | 期限 | 提出先 | 添付書類 | テンプレート |
| 法人設立届出書 | 義務 | 設立日から2か月以内 | 会社所在地所轄の税務署 | 定款のコピー・株主名簿・法人事業概況説明書 | 国税庁 |
| 事業開始等申告書 | 義務 | 設立日から15日〜1か月以内(自治体による) | 都道府県税事務所、市区町村税務課など | 定款のコピー・登記事項証明書など | 自治体により異なる |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 義務 | 開設日から1か月以内 | 会社所在地所轄の税務署 | 特になし | 国税庁 |
| 健康保険・厚生年金新規適用届 | 義務 | 法人設立後5日以内 | 会社所在地所轄の年金事務所 | 登記事項証明書、賃金台帳など | 日本年金機構 |
| 被保険者資格取得書 | 義務 | 報酬を受け取り始めた日から5日以内 | 会社所在地所轄の年金事務所 | 特になし | 日本年金機構 |
提出は任意だが重要な書類とは?
いち:「ここで紹介する書類は、任意ではあるのですが、とても大きなメリットがあるものですので、ぜひ提出を検討してみてください。」
青色申告をするなら提出必須の書類
青色申告の承認申請書
【期限】設立日から3か月以内または第1期の決算日の前日までのどちらか早い日まで
【提出先】会社所在地所轄の税務署
【テンプレート】あり 国税庁
いち:「青色申告とは、複式簿記、貸借対照表と損益計算書を添付して、期限内に確定申告をすると納税額から55万円(e-taxを利用した場合は控除額65万円)の控除がされる制度です。
簡単にいうと、きちんと帳簿をつけて正しく申告をするという前提で、税務上の優遇が受けられる制度です。
青色申告を行うには、あらかじめこちらの書類を提出しておく必要があります。
提出をしないと自動的に“白色申告”になります。」
源泉所得税の納付を簡略化する特例申請書
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
【期限】規定なし
【提出先】会社所在地所轄の税務署
【テンプレート】あり 国税庁
いち:「役員報酬や従業員の給料を支払う際には、所得税をあらかじめ概算で差し引いて、会社が国に納める必要があります。
これを“源泉所得税”といいますが、原則毎月、支払った翌月10日までに納付が必要になります。
この制度は、従業員が少なくて事務処理に時間をかけられない小規模の会社にとっては負担といってもいい制度です。
しかし、納期の特例制度を利用すれば、半年に1回まとめて納めることが可能になります。
届出をしていないと特例は適用されませんので、給与を支払う前に提出しておくことをおすすめします。」
消費税の還付を受けるための課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択届出書
【期限】課税事業者になりたい課税期間の開始日前日まで
【提出先】会社所在地所轄の税務署
【テンプレート】あり 国税庁
いち:「消費税の納税義務がない免税事業者が、任意で課税事業者になる場合に提出する届出書です。
創業から2年間は納税義務が免除される免税事業者になるケースが多いのですが、あえて課税事業者を選ぶことで仕入れや設備投資にかかった消費税を控除できるようになります。
その結果、納税額が減ったり、還付を受けられることがあります。
たとえば、自宅を改装して事務所にするかなえさんの場合などの、創業初期に大きな経費を使う予定があるのであれば、こちらを検討してみても良いでしょう。」
インボイス制度に対応するための登録申請書
適格請求書発行事業者の登録申請書
【期限】登録希望日の前日まで
【提出先】国税庁
【テンプレート】あり 国税庁
いち:「インボイス制度を利用する際に必要な書類です。
インボイス制度の内容は長くなるので、解説を後述します。」
任意提出書類まとめ表
| 名称 | 義務か任意か | 期限 | 提出先 | 添付書類 | テンプレート |
| 青色申告の承認申請書 | 任意 | 設立日から3か月以内または第1期の決算日の前日までのどちらか早い日まで | 会社所在地所轄の税務署 | 不要 | 国税庁 |
| 源泉所得税の納期の特例に関する申請書 | 任意 | 規定なし | 会社所在地所轄の税務署 | 不要 | 国税庁 |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 任意 | 課税事業者になりたい課税期間の開始日前日まで | 会社所在地所轄の税務署 | 不要 | 国税庁 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 (インボイス) | 任意 | 登録希望日の前日まで | 国税庁 | 不要 | 国税庁 |
インボイス制度とは?|登録すべきかどうかの判断ポイント
かなえ:「インボイスってよく聞くようになりましたね。」
いち:「インボイス制度は2023年10月から始まった、正式には、適格請求書等保存方式と呼ばれる制度です。
取引先が、仕入税額控除(仕入れの税金を少なくする)を使うには、インボイスの登録をしている事業者(適格請求書発行事業者)からの請求書じゃないとできなくなったんですよ。」
※経過措置により、2029年9月30日までは一部控除が認められています(控除割合80%→50%→20%と段階的に縮小)
かなえ:「じゃあ、適格請求書発行事業者の登録をしていないと取引相手に迷惑がかかることもあるってことですか?」
いち:「そうですね、その可能性はあります。
かなえさんの取引相手が課税事業者(多くはそう)だった場合、かなえさんがインボイス発行事業者じゃないと、取引分の消費税を相手は控除ができなくなってしまいますから。
結果として取引条件が不利になるとか、税込価格を下げてほしいなんて交渉になるケースもあるみたいですよ。」
かなえ:「登録しないと経営に支障があることがでてきそうですね…」
いち:「そうですね、逆に言えばBtoB(企業と企業)の取引が多くなる予定ならば、登録しておいた方が安心だと思います。
ただし、登録をすると自動的に消費税の課税事業者になりますので、免税事業者のままでいたい場合は慎重な検討が必要です。
つまり、免税事業者のままだとインボイスは発行できませんので、登録するには課税事業者になることがセットというわけです。」
かなえ:「なるほど…悩ましいところですね…
私の場合は、先に教わった“消費税課税事業者選択届出書”のメリットと一緒に考えたらいいのかもしれませんね。」
いち:「はい、おっしゃる通りだと思います。」
届出以外に、会社設立直後にやっておくべきこと
かなえ:「行政機関への届出以外で、設立直後にやっておいた方がいいことってありますか?」
いち:「そうですね、いくつか挙げてみましょう。」
◆事業発足前に検討した方がいいこと◆
1 会計ソフトの導入
2 社内規定の作成や整備
3 補助金や助成金の検討
4 名刺の作成
5 ウェブサイトやSNSの整備など、外部への発信手段を整える
かなえ:「なるほど…言われてみたら確かにやっておいた方がよさそうなことばかりですね。
会社設立後にもまだまだやらなければならない事務処理がたくさんありますね。」
いち:「事務処理などの運営面も含めて“会社”ですからね。
なかなか一つの事に専念できる機会は訪れてはこないかもしれませんね。
それにいずれは雇用のことも考える機会がでてくるでしょう。
雇用についてはまた機会を改めて詳しくお話しすることにしましょう!(雇用編へ)」
ひとり会社設立編まとめ|会社設立後を効率よく進めるために
かなえ:「早く軌道に乗せて人を雇えるまでにしていきたいです。
いつかは事務所をいくつも構えられるような経営者になりたいです!」
いち:「とてもいい目標ですね!
経営者にそういったビジョンがあると日々の運営にも意味が出てきますよね。」
かなえ:「でも…登記が済んで会社が設立されて、もまだこんなにやることがあるんだってちょっと驚きました。
しばらくは会社の土台作りに追われる日々になりそうです。」
いち:「これからは、資金繰りや税務対応、雇用、契約関係など、経営者として判断すべきことがどんどん出てきますし、初めて知ることもたくさんあると思います。
失敗することもあるでしょうが、それも経験ですし、どう乗り越えるかが大切なことだと思います。
焦らずに立ち止まって調べたり、人に相談したりする習慣がついてくれば、自然と会社も育っていくんじゃないでしょうか!」
かなえ:「“ビジョンを持ち”“分からない事は素直に人に聞く”ですね。
はい!全部自分で抱えようとしないで、分からないことはちゃんと調べて、助けを借りるようにします。
そのときは、いちさんも助けてくださいね!」
いち:「はい、これからも何かあれば気兼ねなく声をかけてください!」
ひとり会社設立編終わり。
ひとり会社設立編番外編はこちら